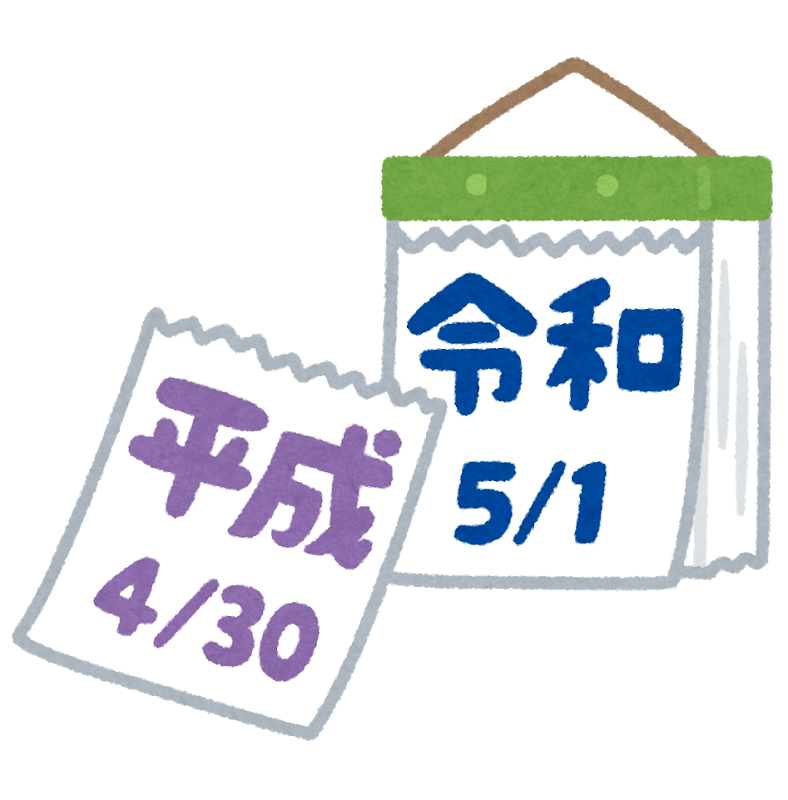2019年5月1日の今日、元号が「令和」に変わりましたね。
元号もそうですけど、鎌倉好きな自分としては天皇が行為を後継者に譲って上皇になられるのが、なんかいいなあと思うわけです。鎌倉幕府を討伐するために兵を挙げた後鳥羽上皇が頭から離れません(笑)
ちなみに状況が出家すると「法皇」になりますね。後白河法皇が有名です。
あ、話がそれてしまいました。今日は歴史ネタではありません。
FP時代に苦労した年齢計算
FPという仕事はクライアントの年齢や期間などが重要なポイントになります。特に年金計算、また贈与で婚姻期間が20年とか。
しかし日本は和暦と西暦を併用しているので、計算するにはちょっとしたコツが必要です。
西暦だけの場合
・1980年生まれの場合、今は2019年なので、2019-1980で39才(年間)って簡単な引算ですが、
和暦が入ってくると
・昭和55年生まれ、今は令和元年。さあ何歳(何年間)? って言われると、うーんって唸ります。
ポイントは元号の終了年を知っておく
明治は45年、大正は15年、昭和は64年、平成は31年となりました。
上記の場合だと、
昭和(64-55)は9年間+平成は(31)は31年間+令和(1)は1年間、で41歳(年間)ですね。
西暦だと、2019年-1980年=39年 あれ?ズレましたね。
改元の場合は、昭和64年と平成元年が同じ1989年を共有しているので、元号重なりを1つ引いてあげないといけません。
今回の計算は、元号を二つ跨いでいるので、2つの重なりを引くんですね。
41歳-2年(元号重なり分)=39歳(年間)となります。
和暦→西暦変換はなかなか難しい
一番簡単なのは、昭和55年をいきなり1980年って導くこと。
・自分の和暦と西暦は覚えちゃうと思うのでそこからのズレを計算していくとか、
・昭和と西暦の下2桁のズレは25だとか
こじつけでやる方法もありますが、自分はあえてそれをしませんでした。
理由は、覚える内容に応用が利かないと思ったから。
下二桁のズレ25を覚えても、それはこの計算にしか使えない。汎用的じゃないと。
であれば、昭和は64年間続いてたって事を知ってたほうが今後ニュースや歴史を学ぶ上でも良いだろうと。
プロとして慣れてる感じを出す
今はインターネットで年数計算もできるし、和暦と西暦の対応表も掲載しているので、上記の計算をできなくても問題ないでしょう。
しかし、相談に乗ってくれているFPさんがこの年齢計算をネットなどを調べずにスムーズに計算しているのを目の当たりにして、決して悪い印象は持たないでしょう。それどころか、このFPさん慣れているな、経験豊富かもって思わせることもできるかもしれません。
クライアントさんを引き付ける行動はこんな小さなところから。
プロって大変ですね(笑)